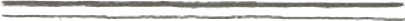§ そうだったの?盆の意味
◆私たち日本人の生活習慣の中に、すっかり定着している 死者を弔う様々な仏教行事があります。
しかし、毎年、当然のように行われているこの行事は、本当の意味で、死者を敬っているのかどうかが、大変疑問なものもあるのです。
夏の時期に行われる「盆」を通し、そのことを、共に考えてみたいと思います。

◆『盆』
すなわち、盂蘭盆会(ウラボンエ)とは、梵語(サンスクリット語)のウラバンナの漢字訳であり、
「逆さ吊りの刑によって苦しんでいる亡者、すなわち地獄に落ちて餓鬼道に苦しんでいる亡霊(死者)を救う、また、慰めること」
を意味します。
仏教の経典のひとつである『盂蘭盆経』には、「釈迦の弟子の目蓮が、ある日、神通力によって亡き母の姿を見たが、その母が、餓鬼道に落ちて、逆さ吊りの刑に苦しんでいるのを知り、これを助けようとして供養したのが初めである。」と記しています。

◆つまり、「盆」の様々な行事は、「地獄に行った先祖の霊を慰めるもの」ということになのです。
「お盆には、地獄の釜の蓋が開いて、ご先祖様が帰ってくるから、道に迷うことのないように、ちょうちんに灯をともしてお迎えするのよ・・。」などと、幼いころに聞かされたものです。
しかし、せっかく、極楽往生するようにと「初七日」「四十九日」の法要をし、高いお金を出して戒名を書いてもらったというのに、一方では、盆の行事をするということは、先祖がみな地獄に行っているということを、認めていることになるのです。
~ 豆知識コーナー ~
『盂蘭盆経(うらぼんきょう)』は、仏教学者たちの一致した意見では、仏陀(ブッダ)の教えではなく、インドの仏弟子たちがおしえたものでもなく、実は、中国の僧侶が書いたものなのです。
そもそも、仏教は、ブッダの死後、約500年ほど経って、『大乗仏教』と、『小乗仏教』に分かれました。
小乗仏教は、「独自で修業して悟りを得よ」というもので、実際にブッダが教えた教えです。
一方、大乗仏教は「他力本願」であり、何者かによって、自分を救ってもらおうという教えです。しかし、これは、ブッダの教えではありません。
ですから、仏教学者たちは、『大乗非仏教説(だいじょうひぶっきょうせつ)』といって、大乗仏教が、もともとのブッダの教えではないことを認めているのです。
そして、この大乗仏教が中国を経て、日本へ伝わるまでに、中国の『儒教』(:孔子の教え)が入り、死霊、祖霊を供養することを教える『盂蘭盆経』ができたのです。
先祖崇拝を語っている盂蘭盆経は、儒教を教えられている中国人に喜ばれ、梁の武帝大同四年に、初めて「盆祭り」が行われたそうです。
また、日本においては、斉明天皇の時代に入って来たようです。いずれにせよ、盆は、仏教の教えとは全く関係ない行事であり、人間の創作した話であると言えます。~

◆『位牌:いはい』
「火事や災害のときには、一番に位牌を持って逃げます・・・。」と言う人が、多いことは、よく知られています。
これは、日本人が、「位牌」を先祖そのものと考えているところから、起こっていることなのです。
さて、この『位牌』の起源は、むかし、日本で仏教が盛んであった時代に、まじめな仏教徒たちが、仏陀の諸戒律を守ろうと努力したことから始まります。
ところが、商人や農家の人たちは、仕事に追われて十分に修業ができないので、一年のある時期を選んで三日から七日ほどの期間、寺参り、または、寺ごもりをして、戒律を守りました。
それが終わると、住職から戒律を守ったという証拠として「戒名」を「鳥の子紙(和紙の一種)に書いて、紙包みにし、その上に「戒名」の二字を書いてもらい、喜んで家に帰ったというのです。
こうして、生前に修業に励んでもらった戒名を大切に保存しておいたのですが、本人が死に、上が次第に古く、汚くなるので、遺族がそれを板にかきかえました。
これが『位牌』の初めです。ですから、位牌に書いている文字や板そのものが大切なのではなく、本人が戒律を守るという努力あってこそ、戒名に意義があるのです。

◆しかし、いつの間にか、仏教徒のこうした熱心な風習が、はやらなくなり、誰でも死にさえすれば、死者に戒名をつけるようになりました。
しかも、お金をたくさんだせば立派な戒名をもらえるというのですから、仏陀の戒律も、今では、金で取引され、商品化しているというわけです。

◆ これは、一例にすぎませんが、私たち日本人が当たり前のように続けている先祖供養の方法は、単に形式化してしまった風俗習慣であることがわかります。
心情的には受け入れにくいことかもしれませんが、熱心に法事、墓参り、盆などの先祖供養をしても、実際には先祖とは何の関係もないことであり、また、これらのことを一切、やめても、先祖を粗末にするわけでも、呪やたたりがあるわけでもないのです。

◆ 真相は?
「人は、死後 どこへいってしまうのか・・・?」
この問題は、以前として人間にとって、大きな謎です。
ところが、直観的に、死後の世界を意識している私たちは、いつ頃からか、死者に対する礼拝をはじめました。
ある者は、恐れから、また、ある者は敬愛から、死者を生きている者同然に、いやそれ以上に敬うべき者として、扱うようになったのです。
しかし、本当のところ、私たちの先祖は、実際には、私たち生きているものに、何を望んでいるのでしょうか・・・。
『私はこの炎の中で、苦しくてたまりません。…私には、兄弟が五人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。』(聖書ルカ16章24~28節)
これは、地獄に落ちて苦しんでいる者のなまの声です。
聖書は、はっきりと死後の世界について語っています。
死後は、永遠の天国か永遠の地獄かの、どちらしかないと、宣言しています。 
◆天国とは、神さまがご存在され、神さまご自身の栄光が満ちあふれる喜びの場所で、そこには、死も苦しみも悲しみもありません。
地獄とは、火と硫黄の燃える裁きの場所で、そこでは何の希望もなく、永遠に苦しみ続けるのです。
それでは、だれが、天国に行き、だれが地獄へいくのでしょうか?
すべての人間は、きよく正しい神様の前に罪人であると聖書は語っています。
『義人はいない。ひとりもいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。~』(聖書ローマ3章10節)
『すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず~』
(聖書ローマ3章23節)
私たち人間は、神様に造られ生かされている存在であるにもかかわらず、神さまの存在を認めず、むしろ、人間の手で造ったものを礼拝の対象としています。
また、憤りやねたみなど、数々の罪にみちた心を持つ者です。
ですから、罪人である私たちは、このままであるならば、死後にさばきを受け、燃える火の池で自らの罪の罰を受けなければならないのです。
◆しかし、幸いなことに、神様は、このような人間を愛してくださり、地獄ではなく、天国へ行ける希望をくださいました。
神のひとり子イエス・キリストが、今から約2000年前に、この地上にお生まれになり、その生涯の最後に十字架にかかられ、全人類の罪の刑罰を身代わりに受けて下さいました。
そして、キリストは死んで終わりではなく、死後三日目によみがえり、ご自分が神であることと救いの確かさを証明してくださいました。

『神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いを通して、価なしに義と認められるからです。』(聖書ローマ3章24節)
さて、あなたは、ご自身の永遠について、どのように備えをしておられるでしょうか。
これは皆さんにとって、とても重大な問題です。
先ほどの聖書の話から、ぜひ、お考えくださいますように。